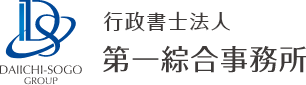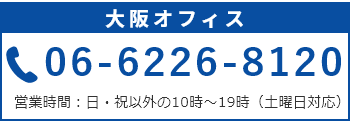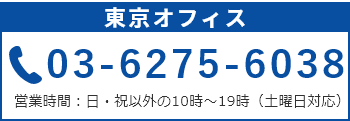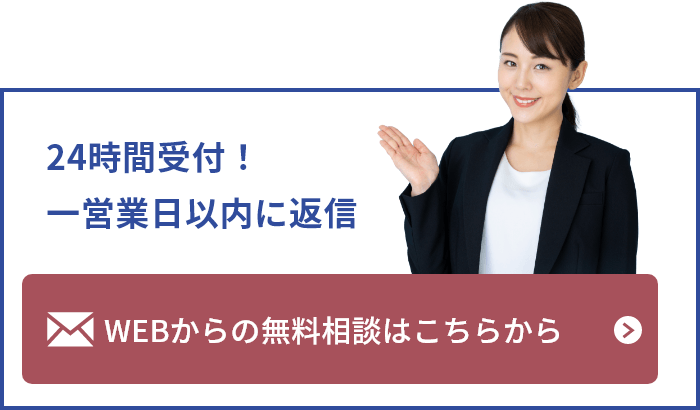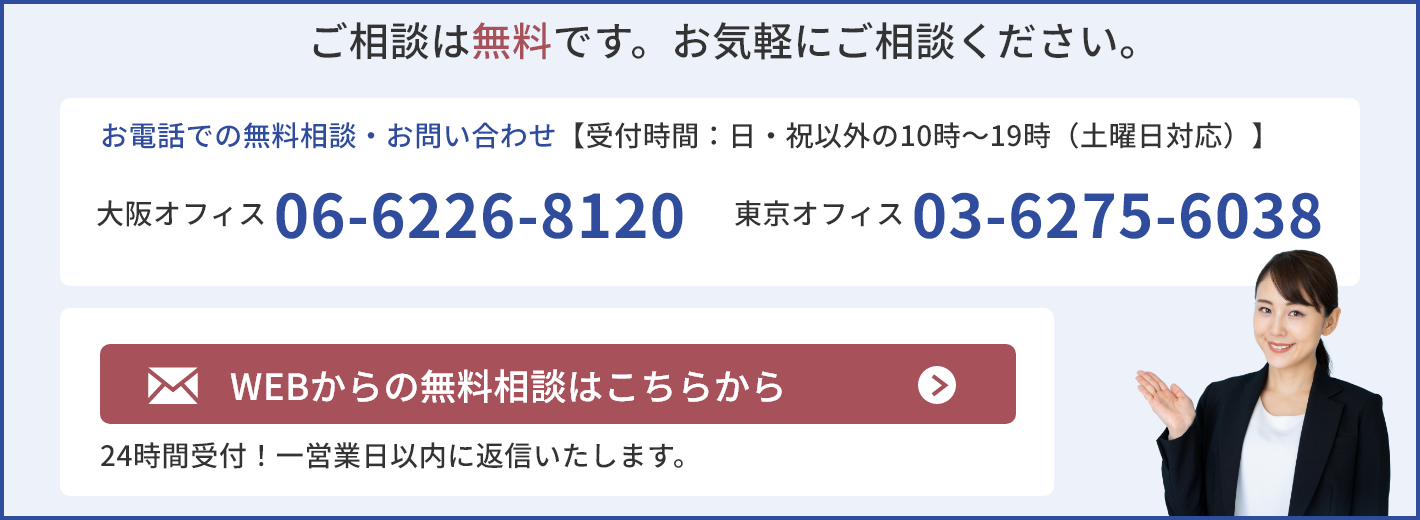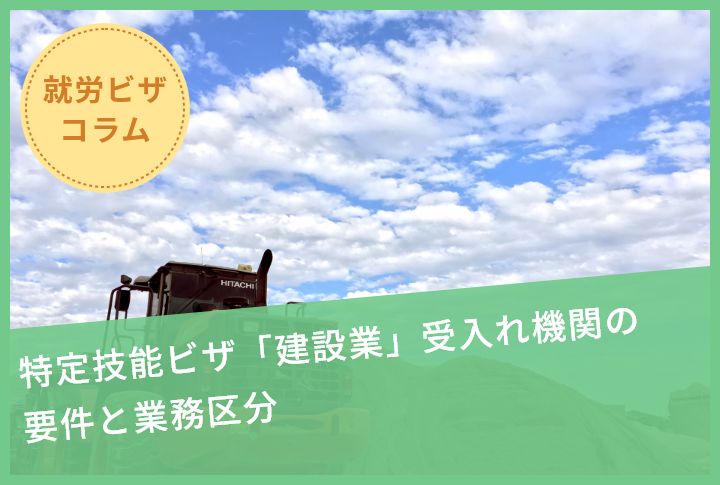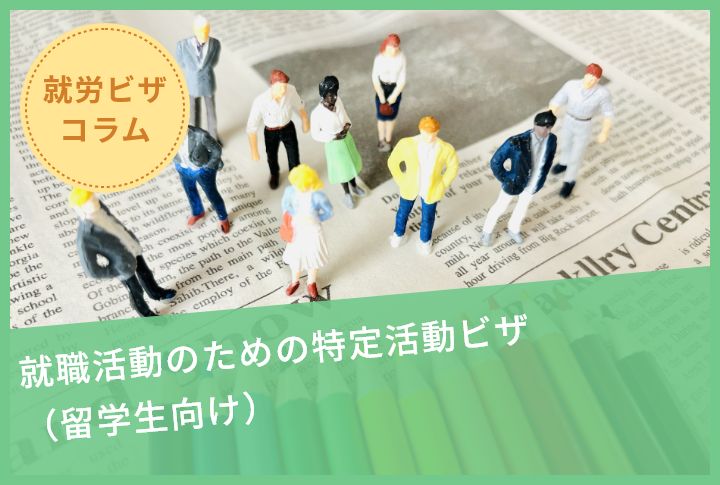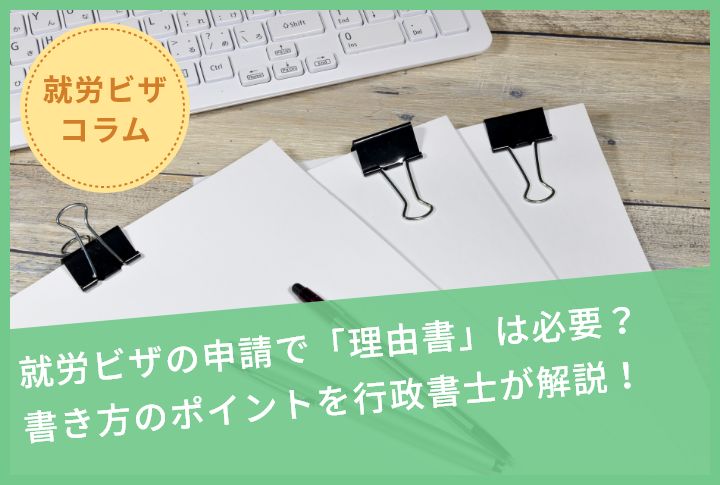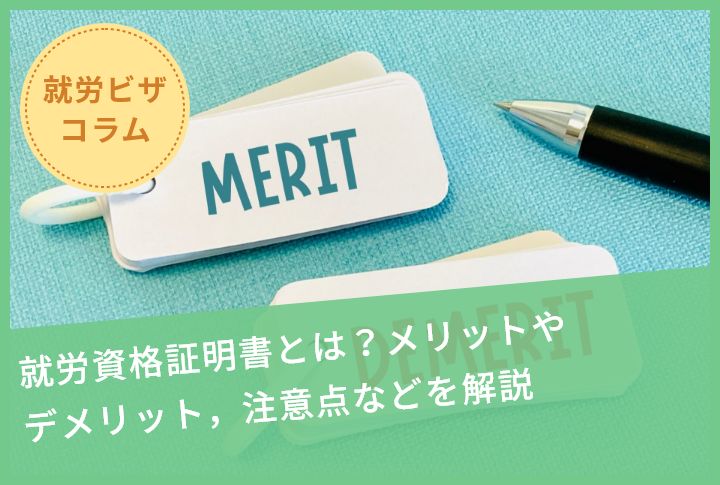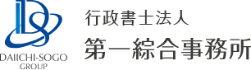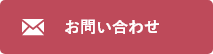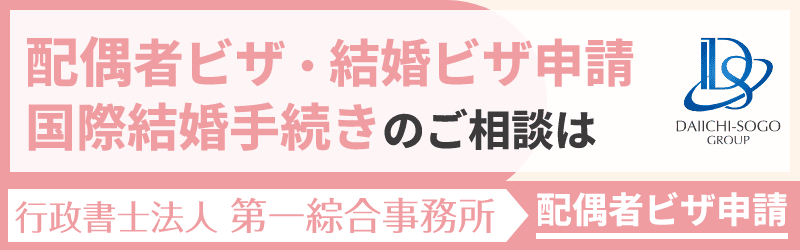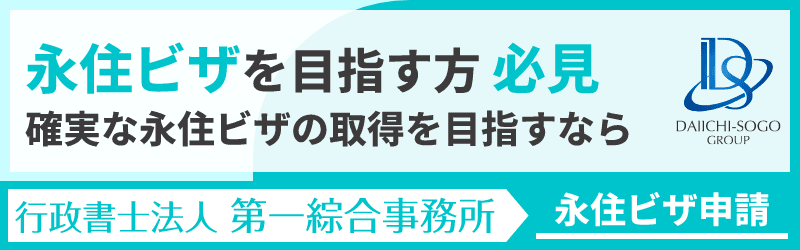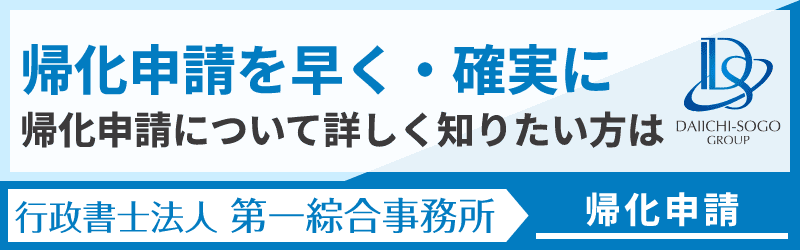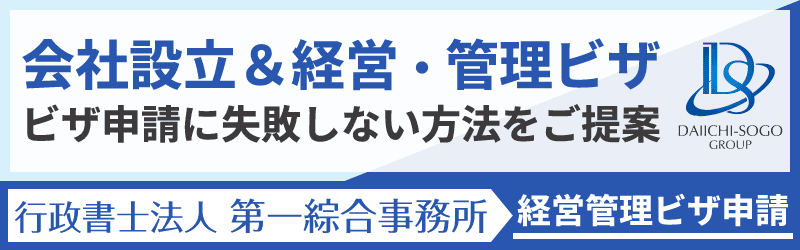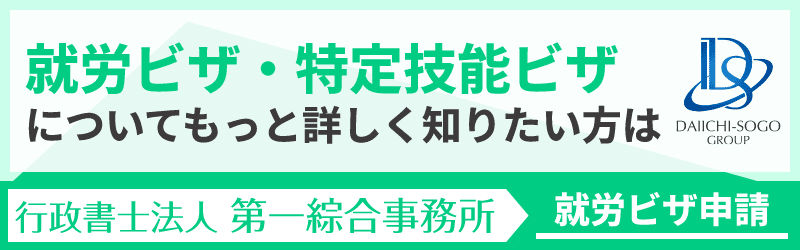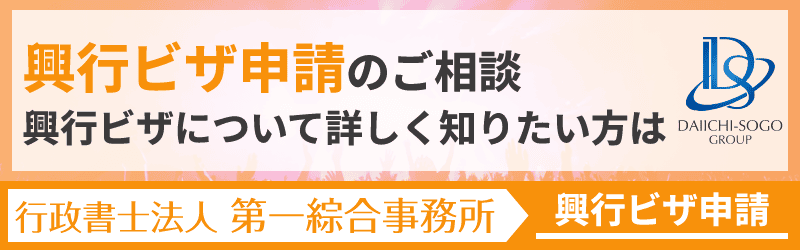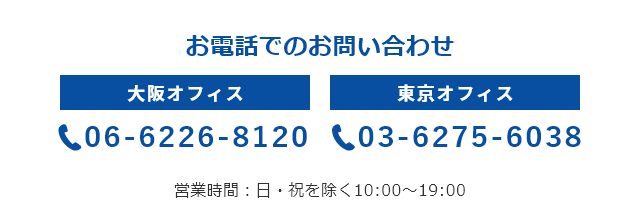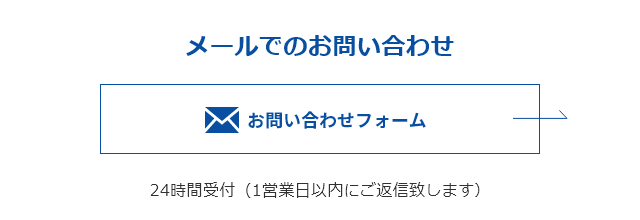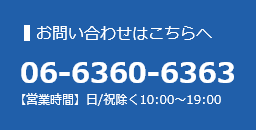研修ビザとは?就労は不可?要件と技能実習との違いを専門家が解説
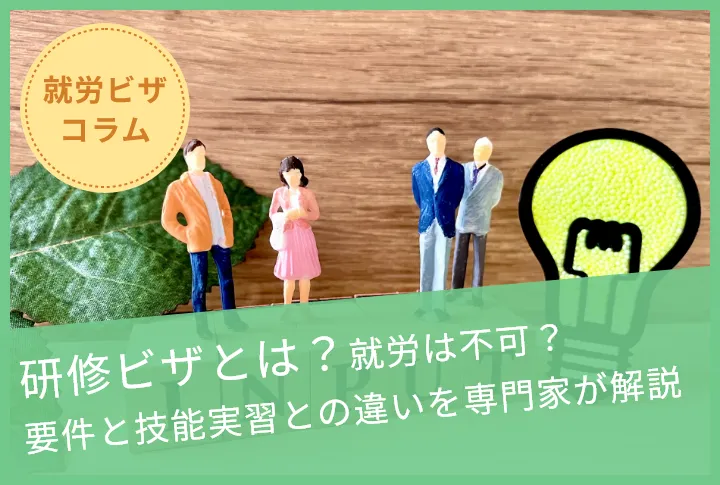
研修ビザで外国人を受け入れたいとお考えの採用担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。研修ビザの取得にあたって,許可の要件や注意すべき点を知っておくとスムーズにビザの申請が行えます。
このページでは,研修ビザについて専門の行政書士が解説をしています。
Index
1.研修ビザとは
研修ビザは,外国人を日本に「研修生」として招き,日本で修得した知識や技術および技能を本国で活用してもらうことを目的としています。諸外国の経済や産業の発展に寄与するという国際協力,国際貢献として推進されているビザです。
研修ビザは,あくまでも日本の技術を修得して本国へ持ち帰るためのビザであり,日本で就労するためのビザでありません。
そのため,労働力を確保するための手段としてこの研修ビザを利用することはできません。
2.研修ビザに該当する職種は?
研修ビザの活動内容(在留資格該当性)は,「本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術,技能又は知識を修得する活動」と定められています。
では,研修ビザで招いた外国人材は,「技術,技能又は知識を修得する活動」であればどのような内容の研修であっても良いのでしょうか?
事例を見ながら,検証していきましょう。
申請人(30歳)は本国で医師免許を取得しており,申請人の本国では未だ取り入れられていない最先端の手術方法(手術支援ロボットを使用)を日本の医療機関で採用している場合,この医療機関は1年間の研修予定で,申請人を研修ビザで招へいすることができるのか。
【事例検証】
研修ビザには「上陸基準省令」が定められていますので,在留資格該当性のみならず上陸基準省令に適合しているかどうかも検証する必要があります。
研修ビザの上陸基準省令は,以下のように定められています。
①「申請人が修得しようとする技術,技能又は知識が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと」
⇒同じ作業を反復して行えば修得できてしまうものであると,研修目的として扱われません。いわゆる単純作業と呼ばれるものは研修ビザには該当しません。
②「申請人が18歳以上であり,かつ,国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること」
⇒日本で修得した技術や知識を本国に持ち帰って活用することを目的としているため,研修スケジュールを明らかにし,滞在年数も示す必要があります。
入管法では,研修期間について具体的な定めはありませんが,実務上では研修期間が2年を超える場合,許可のハードルが高くなります。
③「申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技術,技能又は知識を修得しようとすること」
⇒日本で修得しようとする技術や知識等が,申請人の本国でも簡単に修得できるものである場合は,申請人を招へいする必要性が乏しいと判断されます。
事例に沿って,上陸基準省令に適合しているか確認していきましょう。
①については,最先端の手術方法(手術支援ロボット)が専門知識および過去の経験を活かして修得する技術であることが立証できれば,適合します。
②については,1年間の研修スケジュールを具体的に示すことで適合します。
③については,「申請人の本国で未だ取り入れられていない技術である」という事実と,申請人を招へいする日本の医療機関での最先端の手術支援ロボットを使用した実績を立証することができれば適合します。
今回の事例では,研修ビザの活動内容と上陸基準省令の観点から,申請人を研修ビザで招へいすることは十分可能であると判断できます。
実際に研修ビザを申請するにあたっては,その他の事情もしっかり確認する必要があります。
3.研修ビザの理解に不可欠!実務研修と非実務研修とは?
研修には,実際の業務を行う「実務研修」と,座学や見学が中心の「非実務研修」の大きく2つに分けられます。
このうち,研修ビザでは「非実務研修」を想定しており,「実務研修」については国や地方公共団体,国際機関,独立行政法人など一部の機関が運営する事業で限定的に認められているにすぎません。
また,これらの認められた機関であっても,研修の内容に実務研修を取り入れる場合は,研修全体の3分の2以下とすることが定められています。
一般企業が研修ビザで外国人を呼び寄せる場合,研修内容に「実務研修」を一切含むことができない点に注意してください。
商品を生産もしくは販売する業務,または対価を得て役務の提供を行う業務に従事することで,技術等を修得する研修。
修得する技術について,見学や座学,短期間の体験によって修得する研修。
見学の例:現場見学
座学の例:日本語教育,生活指導,安全教育
短期間の体験の例:試作品の作成
研修内容が実務研修と非実務研修のどちらに該当するのか?はとても重要なことです。
実務研修を含む場合,上陸基準省令に適合しているか等の検討する事項が増え,慎重にビザ申請手続きを進める必要があります。
研修内容について判断に迷う場合は,是非,研修ビザに精通した当社へお問い合わせください。
4.研修ビザの受入れ機関が注意すべき点は?
研修ビザを取得するためには,上記でご紹介した研修内容以外にもう一つ重要なポイントがあります。
それは,研修生を受け入れる側の受入れ体制についてです。
出入国在留管理庁が求めている受入れ機関の基準を確認していきましょう。
①「申請人が受けようとする研修が研修生を受け入れる本邦の公私の機関(以下「受入れ機関」という。)の常勤の職員で修得しようとする技能等について五年以上の経験を有するものの指導の下に行われること」
⇒研修の講師役は,受入れ機関の常勤職員で,研修生が修得しようとする技術等について,5年以上の経験がなければなりません。
②「受入れ機関又はあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること」
⇒研修ビザで招へいした外国人が研修を終えて帰国する際に,予定通り帰国できるよう渡航費の負担など必要な支援措置を行わなければなりません。この基準が設けられているのは,過去に人材不足解消のための手段としてこの研修ビザが悪用され,社会問題となった背景があるからです。このときの反省から,受入機関の在留管理責任を「研修生が帰国するまで」と明確にし,研修修了後の帰国が担保される措置を講じていることを受入の条件としたのです。
なお,帰国担保措置は受入機関だけでなく,受入れをあっせんした機関が対応しても構いません。また,帰国するための渡航費については,入管法上の規定は特にありませんので,研修生に負担させても問題ありません。あくまで措置の一例ということです。
③「受入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し,研修を実施する事業所に備え付け,当該研修の終了の日から一年以上保存することとされていること」
⇒受入れが適正であったかを検証できるように,研修記録を作成し保存しておかなければなりません。在留に関することで何か問題が生じたときには,研修記録の提出を求められることになります。
上記3つのポイントを必ず押さえたうえで,受入機関は研修生を招へいする準備を進める必要があります。
5.研修ビザで再度研修を行うためには?
研修ビザで招へいして研修が終了した後に,再度その外国人を研修生として招へいすることも不可能ではありません。
しかし,本来,研修ビザの目的は本国の発展に寄与するためのものです。そのため,再度研修ビザで招へいするためには,通常の審査ポイントに加えて下記3点についても満たす必要があります。
②前回の研修で学んだ技術等が,本国において活用されていること
③前回と全く異なる業種に関する研修ではないこと
実務上,この3つのポイントと再び招へいする必要性をきちんと明らかにすることで,再度研修ビザ取得を取得することは可能です。
6.研修ビザの申請フロー
研修ビザ申請の流れは以下の通りです。申請人となる外国人が海外にいるか日本にいるかで流れが異なります。
1. 必要書類の収集と在留資格認定証明書交付申請書を作成する
2. 管轄の入管局へ申請書類を提出する
3. 入管審査部門にて審査(数週間~数か月)
4. 在留資格「研修」の認定証明書(COE)が交付される
5. COEを海外にいる外国人へメールで送る
6. 外国人本人が現地の日本領事館で査証の発給を受ける
7. 日本へ入国
1. 必要書類の収集と在留資格変更許可申請書を作成する
2. 管轄の入管局へ申請書類を提出する
3. 入管審査部門にて審査(数週間~数か月)
4. 在留資格「研修」の在留カードが交付される
7.研修ビザの申請に必要な書類
研修ビザの申請に必要となる書類は以下の通りです。
こちらも,申請人となる外国人が海外在住か日本在住かによって,準備する書類が異なります。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 証明写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒
- 研修の内容,必要性,実施場所,期間及び待遇を明らかにする文書
- 帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することを証する文書
- 申請人の職歴を証する文書
- 研修指導員の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書
- 送出し機関(準備機関)の概要を明らかにする資料
- 受入れ機関の登記事項証明書,損益計算書の写し
- あっせん機関がある場合は,その概要を明らかにする資料
- 在留期間許可申請書
- 証明写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート及び在留カードの原本提示
- 研修の内容,必要性,実施場所,期間及び待遇を明らかにする文書
※COE申請の際に提出した写しを提出します。計画に変更がある場合は,変更の内容がわかるように赤ペンで追記して提出します。 - 研修の進捗状況を明らかにする文書
※入管ホームページで報告書のフォーマットがダウンロードできます。
8.研修ビザと技能実習ビザの違い
研修ビザと同じように,日本の技術等を本国に持ち帰って活用してもらうことを目的のひとつとしているビザがあります。それが「技能実習ビザ」です。研修ビザと技能実習ビザは似ているのですが,もちろん同じではありません。この2つのビザの違いを表でまとめてみました。
| 研修ビザ | 技能実習ビザ | |
| 雇用契約 | ない | ある |
| 金銭の支給理由 | 研修手当として支給 | 賃金として支給 |
| 労働関係の各種法令の適用 | 適用されない (準拠することは必要) |
適用される |
研修ビザは,業務に従事するわけではないので雇用契約は結びません。雇用契約がないので賃金を支払うことは認められず,研修で日本に滞在している期間の生活費や交通費は研修手当として支給することになります。
一方で,技能実習ビザは雇用契約を結びますので,賃金として支払う必要があります。この賃金は,同じ業務をしている日本人がいる場合,その日本人と同等以上にしなければなりません。また,労働関連の各種法令が直接適用されますので,強制労働や中間搾取などを行った場合は労働基準法に基づいて処罰されます。研修ビザの場合は,労働関連の各種法令に準拠する必要はありますが,労働ではないので直接適用されることはありません。
9.研修ビザのまとめ
研修ビザは,実務を伴わない研修を3ヶ月から1年間程度実施する場合に取得することが一般的です。
また, 研修ビザは,研修内容や受入れ体制など考慮すべきポイントがいくつかありますが,しっかりポイントを押さえれば,取得できないものではありません。
これから外国人材の招へいをご検討されている企業様がいらっしゃいましたら,是非当社までお問い合わせください。
企業のご担当者様からは「どのビザが適切なのか判断が難しい」という声も多く耳にします。現在の状況をお伺いのうえ,貴社によって最適な方法をご案内させていただきます。