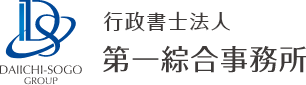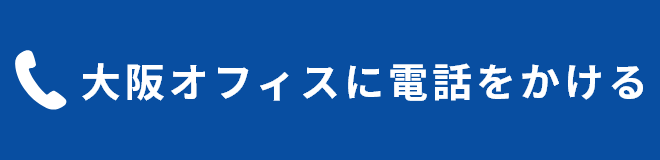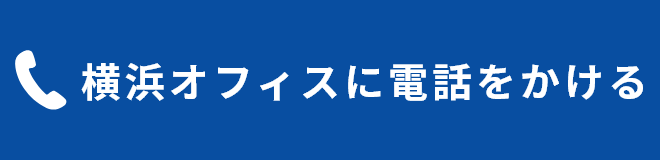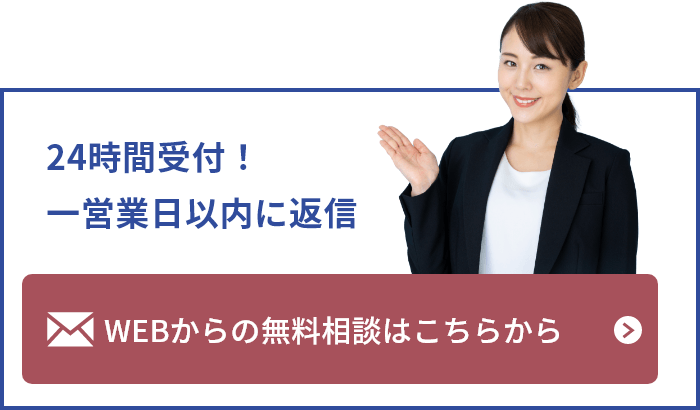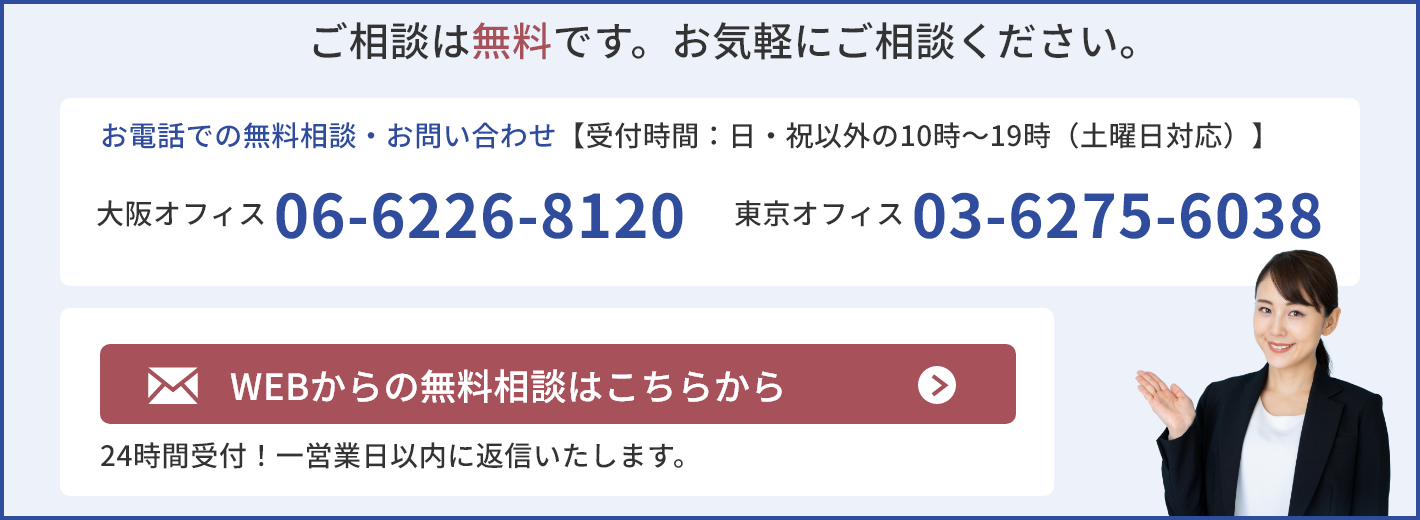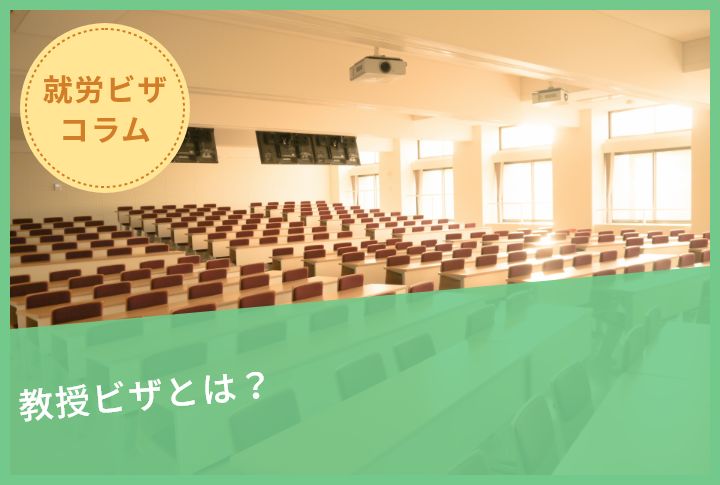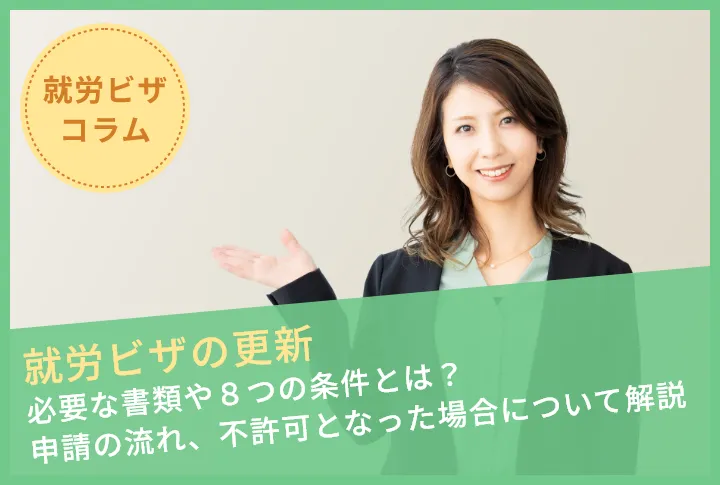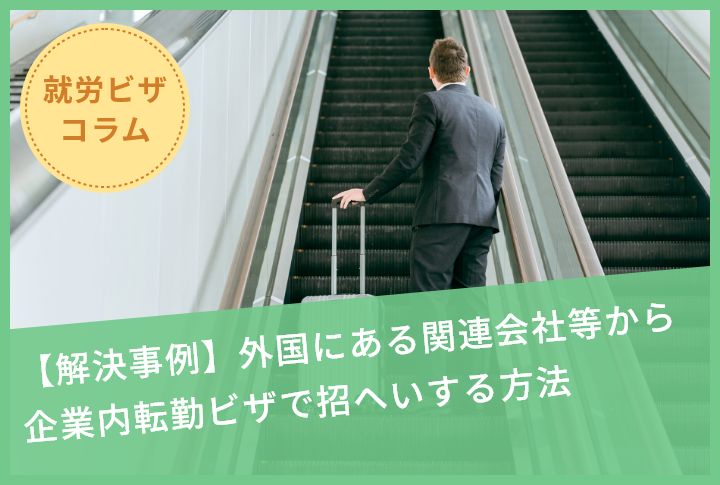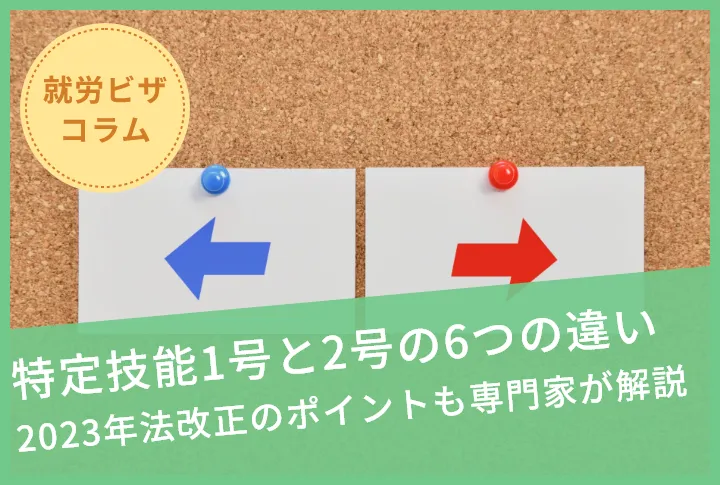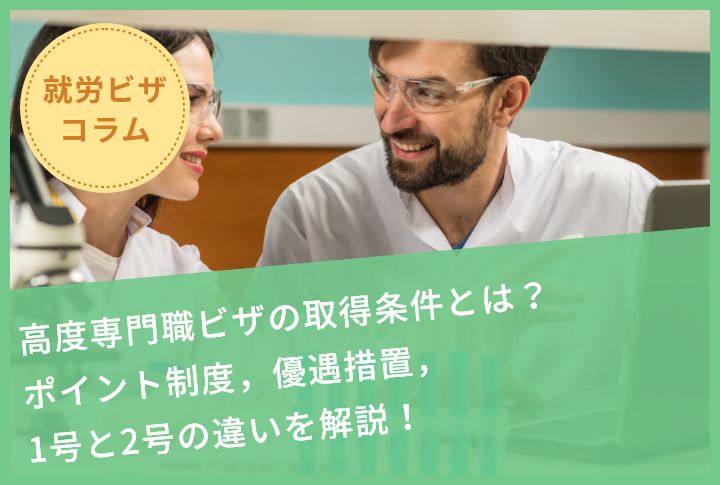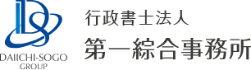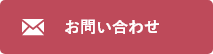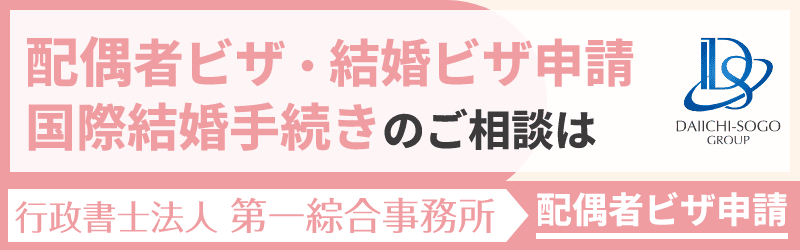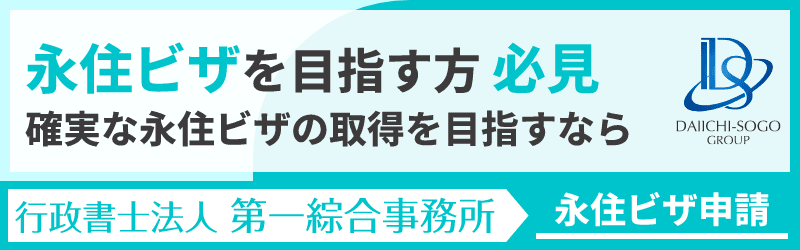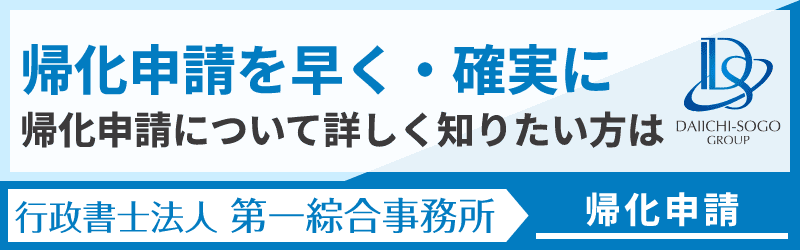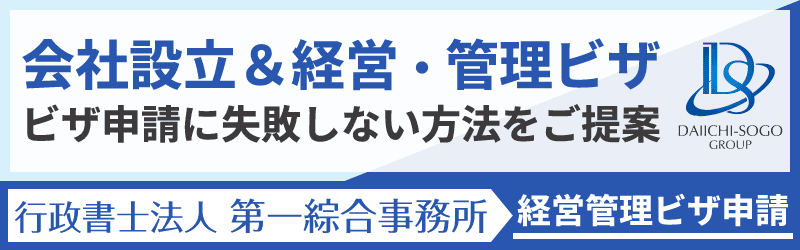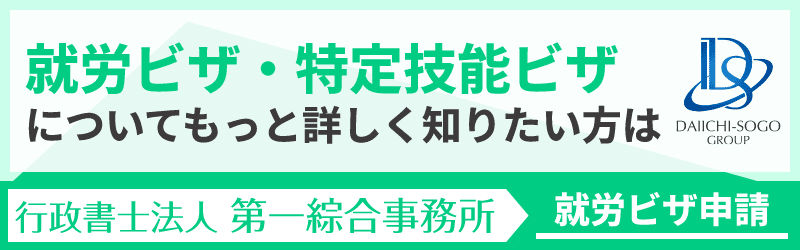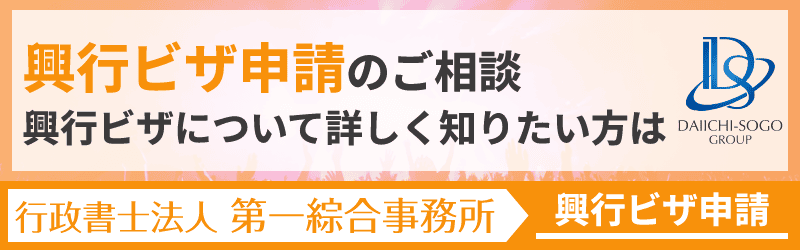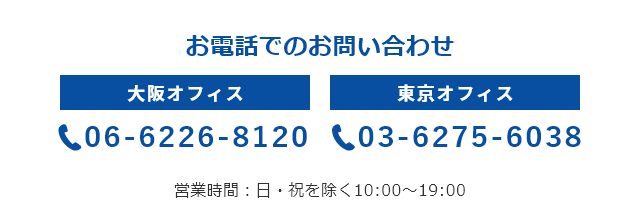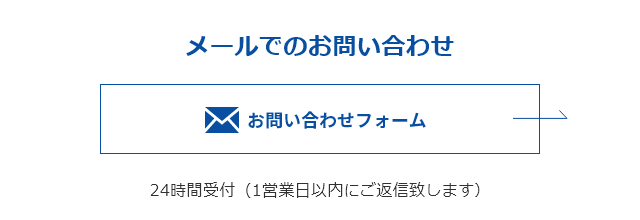就労ビザで5年以上の在留期間を取得する条件とは?1年・3年との違いを解説
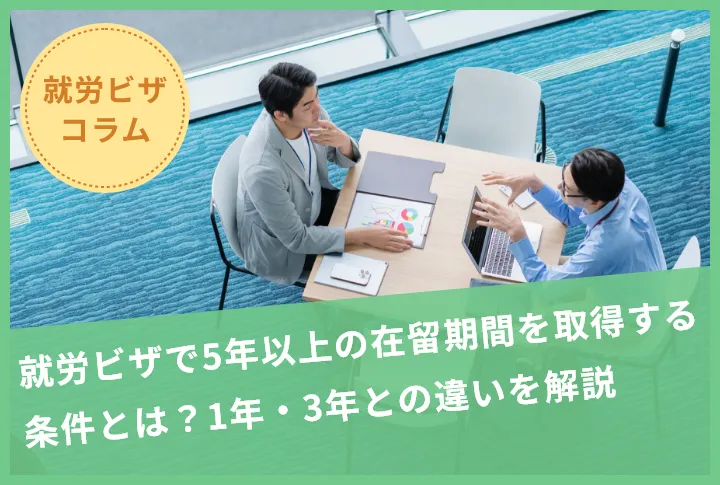
日本で就労ビザを持って働く外国人にとって,在留期間「5年」の取得は,安定した生活基盤を築く上での一つの目標です。
しかし,誰もが簡単に在留期間5年を取得できるわけではなく,出入国在留管理庁による厳格な審査を通過する必要があります。
最長の在留期間を得るためには,勤務先の企業の安定性や申請者自身の在留状況など,いくつかの重要な条件を満たさなければなりません。
この記事では,在留期間5年が許可されるための具体的な条件や,1年・3年との違い,申請時のポイントから取得後の注意点までを網羅的に解説します。
Index
1.就労ビザの在留期間はどのように決まる?1年・3年・5年の違い
就労ビザの在留期間には「5年」「3年」「1年」「3か月」などの複数種類があり,どの期間が許可されるかは,出入国在留管理庁の審査で個別に判断されます。
審査では,申請者の活動内容や在留状況,所属する企業の規模や安定性などが総合的に評価されます。
一般的に,上場企業のような社会的な信頼性が高い企業に勤務している場合や,同じ会社で長期間安定して就労している実績がある場合には,3年や5年といった長期の在留期間が認められやすい傾向にあります。
一方で,設立間もない企業などは,3年や5年ではなく「1年」の許可となるケースが多いです。
(1)在留期間「5年」を取得することで得られる大きなメリット
在留期間「5年」を取得する最大のメリットは,ビザの更新手続き(在留期間更新許可申請)の頻度が減り,時間的・精神的な負担が大幅に軽減される点です。
5年に一度の手続きで済むため,日本での生活やキャリアプランを長期的な視点で設計しやすくなります。
さらに,将来的に永住ビザの取得を検討している場合,在留期間「5年」で許可されていることは非常に有利な要素として働きます。
これは,申請者が日本で安定した生活を送っていることの証明と見なされるためです。
永住許可の要件の一つである「原則として引き続き10年以上日本に在留していること」を満たす上でも,長期の在留実績は社会的信用を高める重要な要素となります。
2.就労ビザで在留期間5年が許可されるための4つの重要条件
就労ビザで最長の在留期間である「5年」を取得するためには,法律で画一的な基準が明記されているわけではありません。
最終的な判断は出入国在留管理庁の裁量によりますが,実務上は審査で重視される複数のポイントが存在します。
- 勤務先の企業の安定性や事業の継続性
- 申請者本人が日本の法令を遵守しているか
- 納税などの公的義務を誠実に果たしているか
- 長期的な雇用の見込みがあるか
…といった要素が総合的に評価され,許可の可否が判断される傾向にあります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
(1)【条件1】勤務先企業が一定の規模や実績を有していること
在留期間「5年」の許可を得るためには,勤務先企業の安定性が重要な要素となります。
出入国在留管理庁は,企業を規模や実績に応じて4つのカテゴリーに分類しており,特にカテゴリー1(日本の証券取引所に上場している企業など)やカテゴリー2(前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人)に該当する企業は,経営が安定していると見なされ,長期の在留期間が許可されやすい傾向にあります。
カテゴリー3や4の中小企業であっても,安定した経営状況を示す決算書類などを提出することで,企業の信頼性や事業の継続性を証明し,5年の許可が出たケースもあります。
※企業のカテゴリーについては「就労ビザのカテゴリーとは?仕組みや対象,区分について解説!」のコラムもご覧ください。
(2)【条件2】申請者本人が法令を遵守し,素行が良好であること
申請者自身が日本の法律を遵守し,善良な在留者であることが在留期間5年を取得するための大前提です。
これには,入管法だけでなく,道路交通法をはじめとする日本のあらゆる法律が含まれます。
重大な犯罪はもちろん,度重なる交通違反なども「素行不良」と判断される可能性があります。
また,入管法で定められている各種届出義務を履行しているかも審査されます。
例えば,転職や退職,勤務先の名称変更や所在地変更,住居地の変更があった場合,14日以内に所定の届出を行う必要があります。
これらの義務を怠ると,在留状況が良好でないと見なされ,期間の決定に不利に働くことがあります。
(3)【条件3】納税などの公的義務を誠実に履行していること
日本に在住する外国人には,日本人と同様に納税や社会保険料の納付といった公的義務が課せられています。
ビザの更新申請,特に5年のような長期の期間を希望する場合,これらの義務を誠実に履行していることがとても重要になります。
具体的には,住民税や所得税を納期内にきちんと納めているかが厳しくチェックされます。
申請時には課税証明書や納税証明書の提出が求められ,これらの書類によって納付状況が確認されます。
もし未納や滞納があれば,在留期間が短縮されたり,最悪の場合は更新が不許可になったりする直接的な原因となります。
(4)【条件4】長期にわたる安定した雇用が見込まれること
申請者が現在の勤務先で,将来にわたって長期間安定して雇用される見込みがあるかどうかも,在留期間を決定する上で重要な判断材料です。
これは,雇用契約書の内容によって判断される部分が大きく,契約期間が「期間の定めなし」,つまり無期雇用契約であることが望ましいとされています。
有期雇用契約であっても,複数回の更新実績があり,今後も契約が継続される蓋然性が高いと判断されれば,長期の在留期間が許可される可能性はあります。
一方で,頻繁に転職を繰り返している経歴がある場合,雇用の安定性に欠けると見なされ,審査に不利に働くことがあります。
一つの企業で着実にキャリアを積んでいる実績は,長期雇用の見込みを示す上で有利な評価につながります。
3.要注意!在留期間が1年や3年に短縮されてしまうケース
これまでに3年や5年の在留期間が許可されていたとしても,その後の状況変化によっては,次回の更新時に期間が短縮されることがあります。
審査は更新の都度行われるため,過去の実績が将来を保証するものではありません。
例えば,勤務先の経営状況の悪化や申請者自身の転職,公的義務の不履行など,安定性や信頼性に懸念が生じた場合,許可される在留期間が1年や3年に短くなる,あるいは更新自体が不許可となるリスクも存在します。
どのような状況が期間短縮につながるのかを事前に把握しておくことが重要です。
(1)所属企業の経営状況や信頼性に懸念があると判断された場合
申請者本人に問題がなくても,所属する企業の経営状況や信頼性が低いと判断された場合,在留期間が短縮されることがあります。
例えば,勤務先の業績が著しく悪化している,または赤字決算が続いている状況では,雇用の安定性が低いと見なされる可能性があります。
また,企業が税金や社会保険料を滞納している,あるいは過去に不法就労者を雇用していたなどの法令違反が発覚した場合も,その企業自体の信頼性が問われます。
審査では申請者個人の状況だけでなく,所属機関の健全性も一体として評価されるため,企業の経営状態が在留期間の決定に直接的な影響を及ぼすことを理解しておく必要があります。
(2)転職直後など雇用の継続性がまだ示せていない場合
転職はキャリアアップの一環として認められていますが,在留期間の更新申請のタイミングと重なると,期間の判断に影響を与えることがあります。
特に,前職を退職して新しい会社に入社してから日が浅い段階での更新申請は注意が必要です。
新しい職場での勤務実績がまだ少ないため,審査官が長期的な雇用の安定性や継続性を判断するのが難しくなります。
そのため,これまでは3年や5年の期間が許可されていたとしても,転職直後の更新ではまず「1年」の在留期間が許可され,新しい職場での勤務状況を一年間見た上で,次回の更新時に改めて長期の在留を認めるか判断するという対応が取られることが少なくありません。
(3)納税や入管法上の届出を適切に行っていない場合
納税や社会保険料の納付,入管法で定められた届出といった公的義務を適切に履行していない場合,在留期間が短縮される直接的な原因となります。
特に住民税の未納や納付遅延は,在留状況が良好でないと判断される典型的な例です。
また,転居した際の市区町村役場への届出や,勤務先を変更した際の入国管理局への届出を怠っている場合も,法令遵守の意識が低いと見なされます。
これらの届出は,日本での在留状況を正確に把握するための重要な手続きであり,これを怠ると,次回の更新時に在留期間が1年に短縮されるなどの不利益を受ける可能性が高まります。
日頃から自身の義務を正しく理解し,履行することが求められます。
実際に,それまで5年で許可されていた方が,転職の届出をしていなかったために更新で1年になってしまったというケースもありました。
4.在留期間5年の取得を目指すための申請準備のポイント
在留期間「5年」の取得を目指す場合,単に必要最低限の書類を揃えて更新申請を行うだけでは不十分なことがあります。
自身が長期の在留に値する安定性と信頼性を備えた人材であることを,客観的な資料に基づいて積極的に証明していく姿勢が重要です。
企業の安定性のアピールから,公的義務の履行証明,そして日本での将来設計を具体的に示すことまで,入念な準備が「5年」許可の可能性を高めます。
ここでは,申請準備における具体的なポイントを解説します。
(1)企業の安定性を示す客観的な資料を添付してアピールする
勤務先が上場企業などではない場合,企業の安定性や継続性を客観的な資料で示すことが有効です。
具体的には,企業の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しや,直近年度の決算文書(貸借対照表,損益計算書など)を任意で提出することが考えられます。
これらの書類は,企業の売上規模や利益,従業員への給与支払い状況などを具体的に示すものであり,経営が安定していることの有力な証明となります。
また,企業のパンフレットやウェブサイトのページを印刷したものなど,事業内容を分かりやすく説明する資料を補足的に添付することも,審査官の理解を助ける上で役立つでしょう。
(2)公的義務の履行を証明する書類を漏れなく提出する
納税義務をきちんと果たしていることを証明するために,お住まいの市区町村役場で発行される「課税証明書」や「納税証明書」を提出します。
これらの書類は,直近の所得額と,それに対する住民税がきちんと納付されているかを示すものです。
取得した証明書に未納額の記載がないことを必ず確認してください。
万が一,「納付期限が過ぎた未納分」があった場合は,市町村役場に確認して納付できるものは早めに納付しましょう。納付後に改めて,未納分がない納税証明書を発行してもらいます。
また,場合によって社会保険の納付状況についても確認されることがあるため,ご自身の加入状況や納付記録を正確に把握し,必要に応じて証明書類を準備しましょう。
(3)提出書類に不備や矛盾がないか入念にチェックする
申請書類に記載する内容と,添付する証明書類の内容に矛盾がないか,提出前に必ず確認してください。
例えば,申請書に記載した年収と,課税証明書に記載されている所得額に大きな乖離がある場合,その理由について合理的な説明が求められます。
また,必要書類が揃っているか,各証明書の有効期限は切れていないかといった基本的なチェックも怠らないようにしましょう。
書類の不備や矛盾点は,審査を遅らせる原因になるだけでなく,申請内容全体の信憑性を損なうことにもなりかねません。
特に転職などを経験している場合は,情報が複雑になりがちなので,より一層慎重な確認が必要です。
書類については,ビザ申請を専門に扱っている行政書士などにサポートを依頼するのもおすすめです。
行政書士法人第一綜合事務所では,申請する方一人ひとりの状況に合わせた最適な「必要書類リスト」を作成し,
過不足ない書類で申請するお手伝いをさせていただいております。
日本の役所書類の取得も代行しますので,平日の日中はお仕事で役所に行くことができない方におすすめです。
5.在留期間5年を取得した後に気をつけるべきこと
念願の在留期間「5年」を取得できたとしても,それで将来の安定した在留が完全に保証されたわけではありません。
在留期間はあくまで次回の更新までの期間であり,その間の過ごし方によっては,次の更新で状況が変わる可能性もあります。
特に,転職による勤務先の変更や,在留中に法令違反や公的義務の不履行があった場合,次回の審査に大きな影響を及ぼすことがあります。
長期の在留期間を得た後も,引き続き法令を遵守し,安定した生活を維持する意識が求められます。
(1)転職によって次回の更新時に在留期間が見直される可能性
在留期間5年の有効期間中に転職した場合,次回の在留期間更新時には,新しい勤務先の状況が改めて審査の対象となります。
例えば,安定した大企業から,設立して間もない小規模なベンチャー企業へ移った場合,企業の安定性が以前よりも低いと判断され,在留期間が3年や1年に短縮される可能性があります。
また,転職後の職務内容が,現在保有している在留資格の活動範囲に合致しているかも重要なポイントです。
職種が大きく変わる場合は,いま持っている就労ビザではなく,別のビザに変更が必要になる場合もあります。
転職を検討する際は,自身のキャリアプランだけでなく,ビザへの影響も考慮に入れることが重要です。
(2)在留中の義務違反は将来の在留資格に大きく影響する
在留期間が5年あるからといって,その間に交通違反を繰り返したり,納税を怠ったりすると,その記録は残り,次回の更新審査や将来の永住許可申請の際に不利に働きます。
特に,税金や社会保険料の未納・滞納は注意が必要です。次回の更新申請では大きな影響はありませんが,永住申請では大きな影響があります。
「納期限までに正しく納付する」ことが永住審査においても重要です。
6.まとめ
就労ビザにおける在留期間「5年」の取得は,申請者本人の適法性だけでなく,所属する企業の安定性や事業の継続性も含めて総合的に判断されます。
「こうすれば5年になる」という明確な基準がないため,何をどうしたらいいのかわからないという声もよく聞きます。
就労ビザの申請手続きについてわからないことや不安なことがあれば,ぜひ行政書士法人第一綜合事務所の無料相談をご利用ください。
オフィスは東京・横浜・大阪にありますが,オンラインや電話での無料相談でしたら全国どこからでもご利用いただけます。