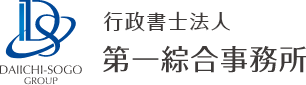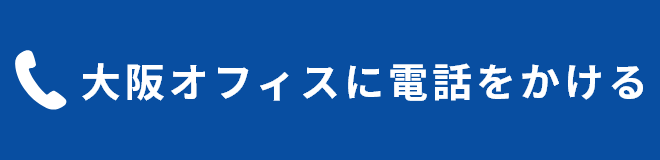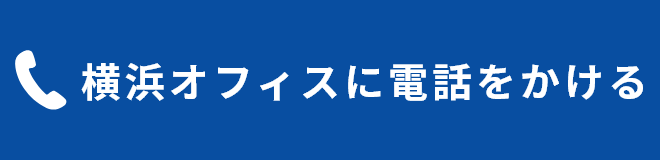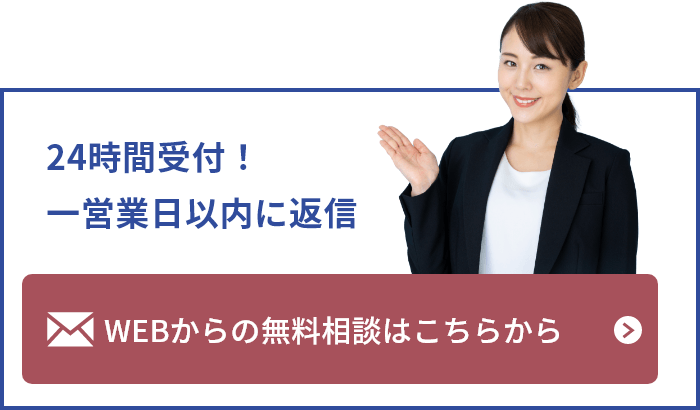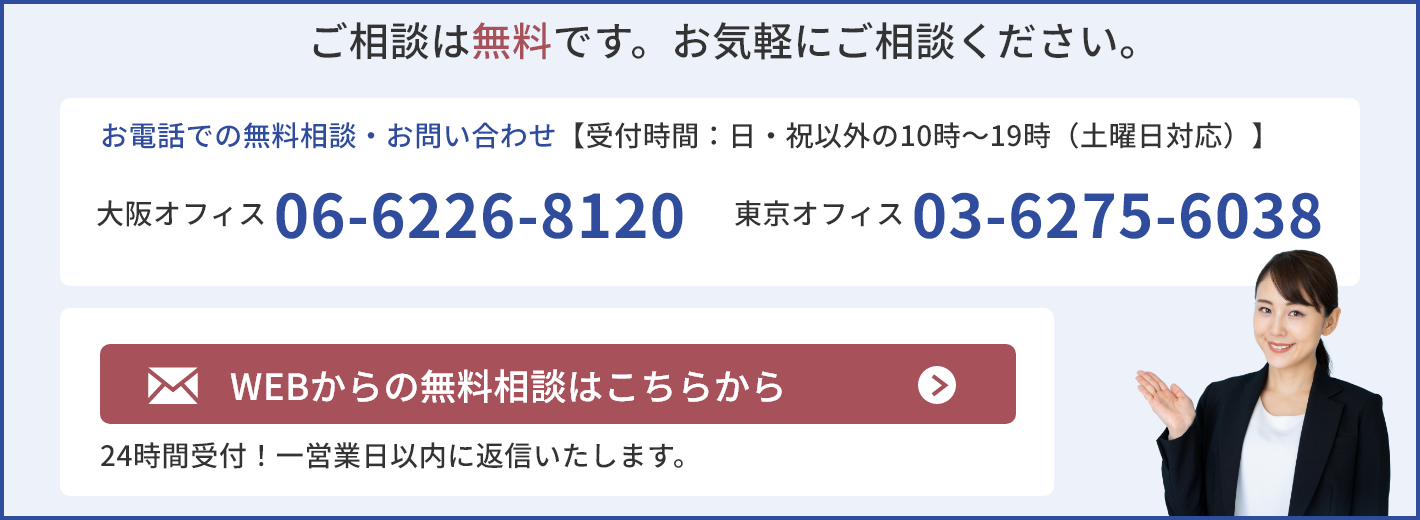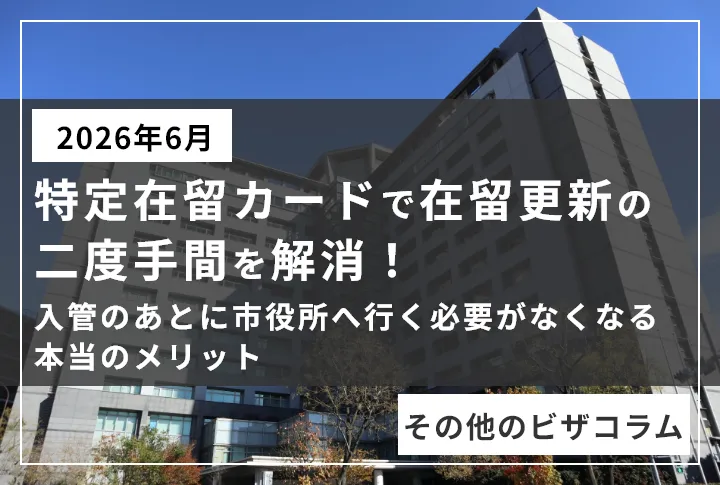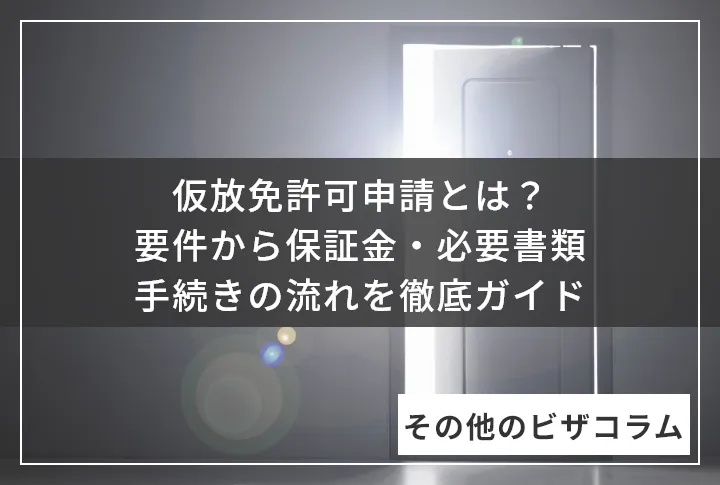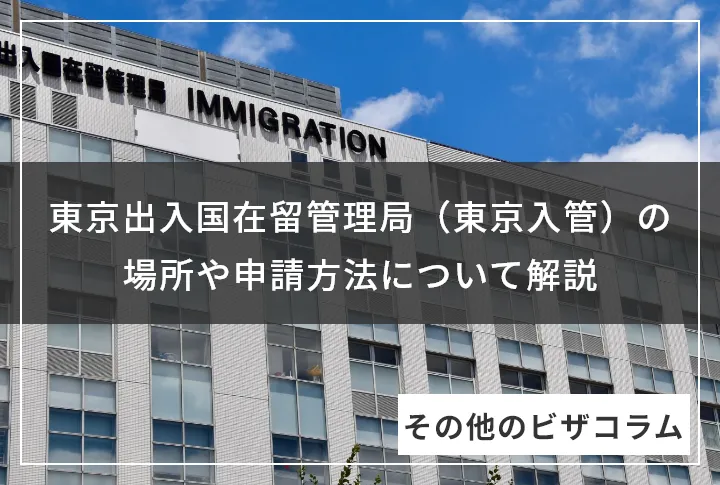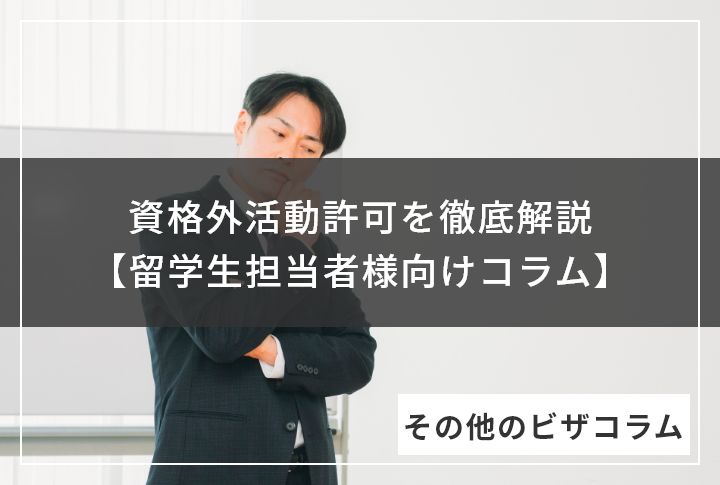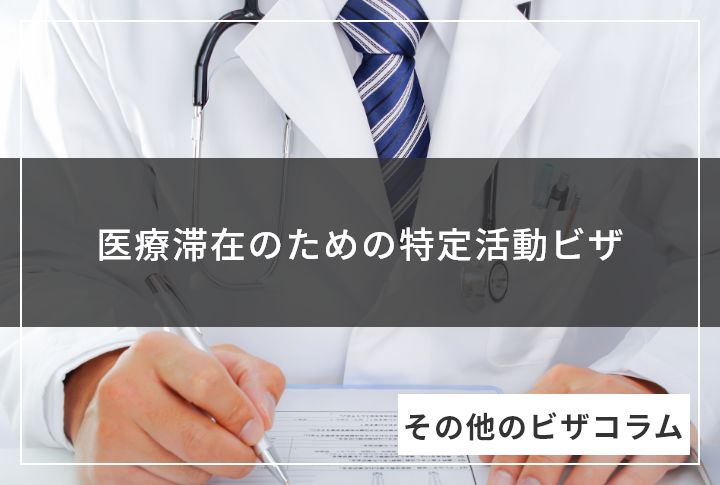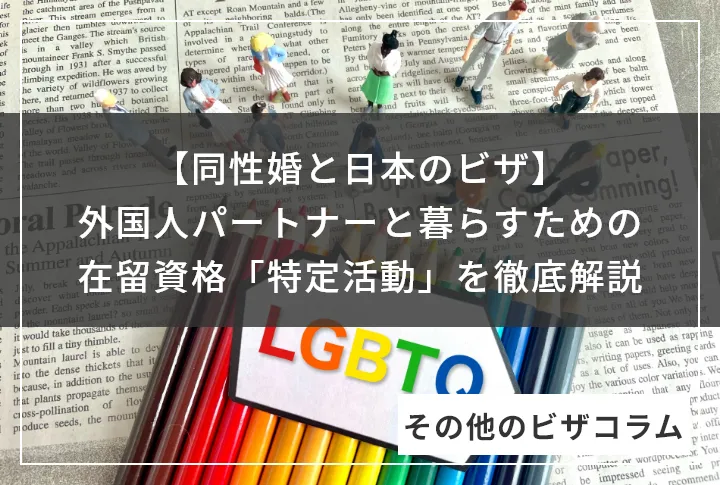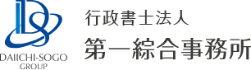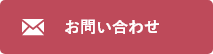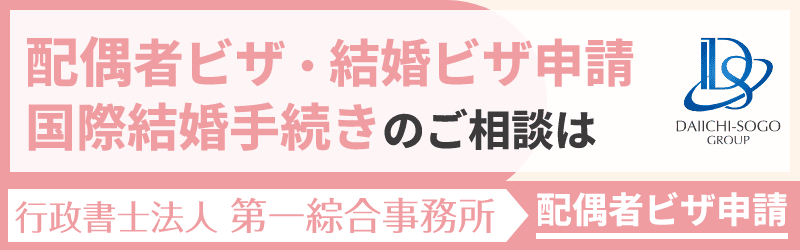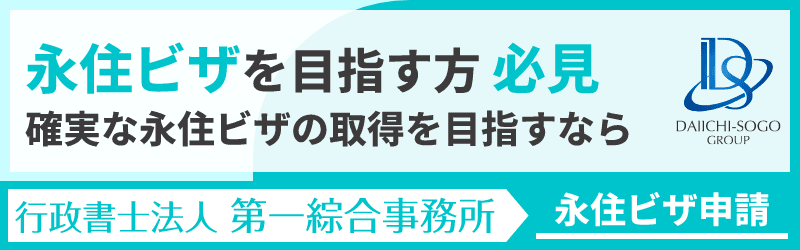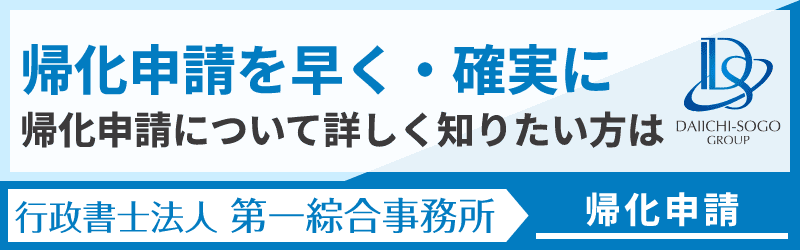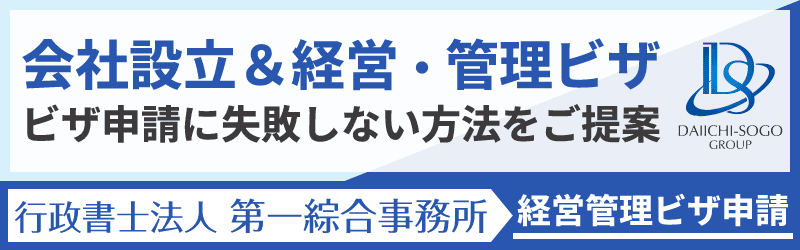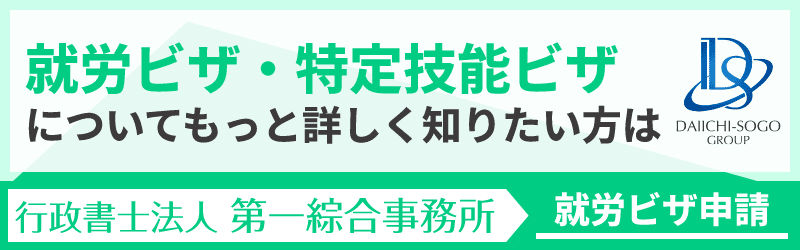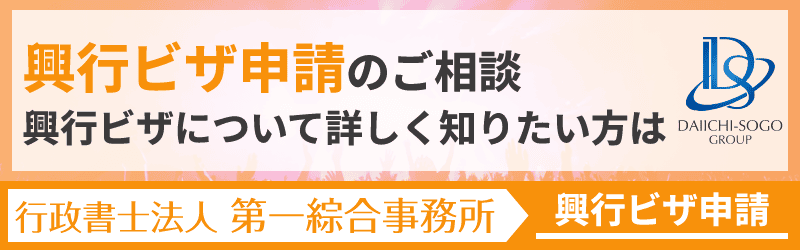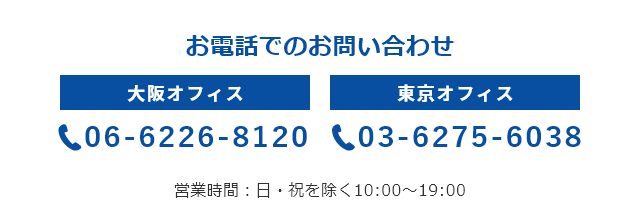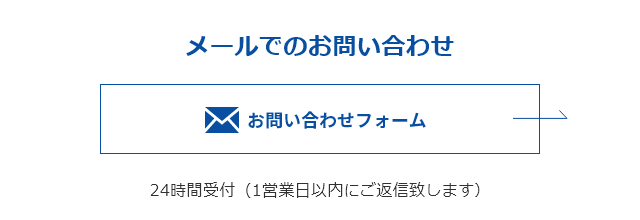【2025最新】ビザの変更と更新のガイドラインを行政書士が解説
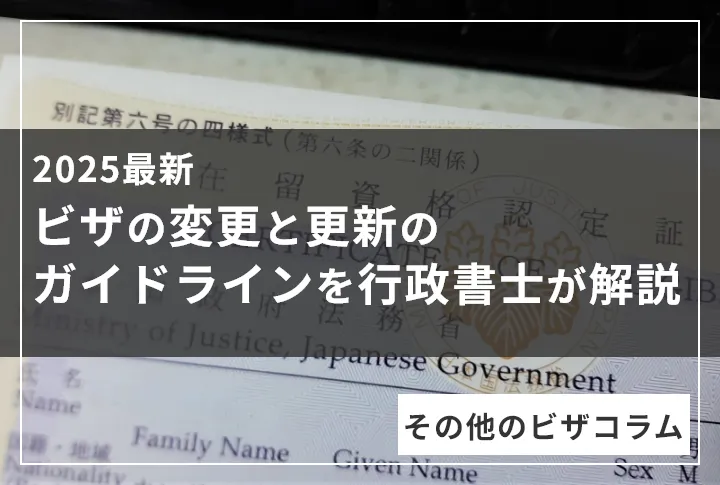
ビザ(在留資格)の変更,在留期間の更新は,入管法で「法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可する」とされており,相当の理由があるかどうかの判断は,法務大臣の自由な裁量に委ねられています。
入管庁では,申請人の方が日本で行おうとする活動の内容や,これまでの在留の状況,在留の必要性などを総合的に見ていますが,どういう基準で見ているか?について,「ガイドライン」を公表しています。本コラムではこの「ガイドライン」について,2025年10月の一部改正内容もふまえて解説していきます。「ガイドライン」の内容を知ることで,次回の更新や変更のときに困らないよう前もって準備することができるようになります。ぜひ最後までお読みください。
Index
1.ガイドラインとは?
冒頭でも触れたとおり,「ガイドライン」とは,許可の判断基準の一部をある程度明確にしたものです。
変更や更新の手続きだけでなく,「永住ビザ」や「経営・管理ビザ」,「特定技能ビザ」などでもガイドラインが公表されています。
ビザの変更または更新ガイドラインには,以下の8つの項目について基準が公表されています。
2)法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
3)現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
4)素行が不良でないこと
5)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
6)雇用・労働条件が適正であること
7)納税義務等を履行していること
8)入管法に定める届出等の義務を履行していること
それぞれの項目について,解説していきます。
1)行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
>>変更または更新するビザが,今後の滞在目的と合致していないとダメ
ビザ(在留資格)は,それぞれ活動内容が入管法で定められています。その内容と合致していない場合は,変更または更新申請しても許可されません。
日本人と結婚して「日本人の配偶者等」ビザで滞在していたが,離婚した。
⇒日本人の配偶者ではなくなったので,配偶者ビザを更新することはできません。
2)法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
>>入国審査の基準もちゃんとクリアしていないとダメ
上陸許可基準とは,外国人が日本の空港などに到着したあとに行われる入国審査の基準のことで,省令として定められています。上記1のとおり,日本に在留するには「在留資格の活動内容に合致していること」が必要ですが,それにプラスして上陸許可基準に該当していなければ日本に入国できません。2つの関門があるイメージです。
上陸許可基準は入国するときの審査基準ですが,入国したらもう関係なし!…ではなく,変更または新の審査でも確認しますよ,ということがガイドラインに明記されています。
3)現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
>>今持っているビザの活動をしていないならダメ
ビザにはそれぞれ活動内容が決まっていることを解説しましたが,今持っているビザの活動状況についても確認されます。定められた活動をしていなかった場合,変更または更新の審査でマイナスの評価となります。
- 留学ビザを取って専門学校に入学した方が,半年後に退学してしまい,「留学」ビザのまま在留し続けている
- ビザを取った後,長期にわたって日本を出国していた
⇒許可された活動をしていないという判断になり,変更または更新が不許可になる可能性があります。
これまでは,長期出国していた場合についてガイドラインには明記されていませんでしたが,実務上は不許可になるケースが多くあり,「暗黙の事実」として知られていました。直近の改正で,長期出国はマイナス評価になることがハッキリと記載されるようになりました。
4)素行が不良でないこと
>>法律違反や犯罪をしていたらダメ
【例えばこんなケース】
- 退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為 不法就労をあっせんする行為
⇒この2つは,ガイドライン上で「素行が不良となる具体例」として挙げられています。
5)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
>>生計が不安定すぎるとダメ
生活していくうえで必要な分の収入があり,今後もそれが見込めることが必要です。これは世帯全体で判断されますので,申請人ご本人が無職で収入がなかったとしても,世帯で収入があれば大丈夫です。また,生活保護の受給などがあったとしても,人道上の理由が認められれば在留できる場合もあり,ここは柔軟に判断されています。
世帯全員が無職で生活保護を受給しており,この先もその状態が変わらなそう
⇒人道上の理由等が認められない限り,変更または更新は許可されない可能性が大きいです
6)雇用・労働条件が適正であること
>>労働関連法令に違反する労働はダメ
外国人の方であっても,日本で就労する場合は日本の労働関連法令が適用されます。そのため,これに違反する雇用契約や労働条件になっている場合は許可されません。
- アルバイトにも関わらず,週28時間以上働くことができる契約になっている
- 業務内容が在留資格上認められていないものになっている
ただ,これはすでに所管官庁から会社側へ勧告などが行われていて,是正される見通しがあればその旨考慮されます。
7)納税義務等を履行していること
>>税金を払えるのに払わないのはダメ
納税義務がある方は,きちんと税金を納付していることも確認されます。未納があったり滞納があったりしても,それだけで不許可になることはありませんが,悪質だと判断された場合は不許可になる可能性が大きいです。
- 未納分となっている金額が高額になっている
- 十分払うことができる資力があるのに意図的に払っていない
8)入管法に定める届出等の義務を履行していること
>>入管法で決められた届出をしていないのはダメ
入管法では,在留カードを交付している外国人(一部除く)に対して一定の「義務」を課しています。
この義務を正しく履行していない場合,変更または更新でマイナスになっていまいます。
- 初めて入国した際の「住民登録」は,14日以内に行う
- 引っ越した際の「住所変更」は,14日以内に行う
- 氏名,生年月日,性別,国籍/地域が変わったときは,14日以内に届出する
- 在留カードの再交付が必要になったときは,その手続きを14日以内に行う
- 在留カードの返納が必要になったときは,14日以内に返納する
- 転職や退職をしたら,雇用契約先の情報を14日以内に届出する
- 離婚や死別をしたら,その情報を14日以内に届出する
転職したのに届出をせず更新申請した場合,在留期間が短くなってしまうケースがあります。
うっかり届出を忘れても,特に通知や連絡がない点に注意してください。
2.社会保険の加入状況も確認されることに
そのほか,変更または更新ガイドラインでは,健康保険証の提示も必要であることが明記されました。これは,社会保険に加入しているかどうかを確認するためです。
2024年12月から従来のカードタイプの健康保険証は廃止され,マイナンバーカードに統合されました。このため,カード型の健康保険証を持っていない方もいらっしゃると思います。
このような場合は,マイナポータルにログインして資格情報を表示させた画面キャプチャなどを提出することになります。
3.すべてクリアしていても不許可になる場合がある
以上が,ビザの変更または更新許可のガイドラインです。
一点注意したいことは,8つの項目すべてをクリアしていても,許可されないケースもあるということです。
それは,ガイドラインにもしっかり書かれています。
“1の在留資格該当性については、許可する際に必要な要件となります。また、2の上陸許可基準については、原則として適合していることが求められます。3以下の事項については、適当と認める相当の理由があるか否かの判断に当たっての代表的な考慮要素であり、これらの事項にすべて該当する場合であっても、すべての事情を総合的に考慮した結果、変更又は更新を許可しないこともあります。”
気になることがあれば専門家にご相談を!
ビザの変更,更新で気になることがあれば,ビザ申請に精通した専門家にぜひご相談ください。
特に申請件数が多い事務所であれば,過去の事例から「許可が取れる」「許可は取れない」のアドバイスを受けることができるでしょう。
行政書士法人第一綜合事務所は,ビザ申請に特化した国内でも珍しい行政書士法人です。初回のご相談は無料ですので,ぜひお気軽にご利用ください。日本語だけでなく,英語,中国語,ベトナム語,韓国語,タイ語にも対応しています。