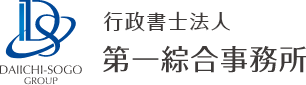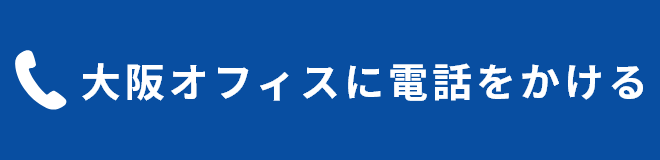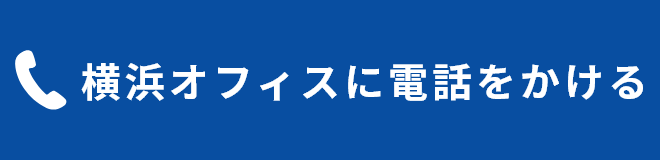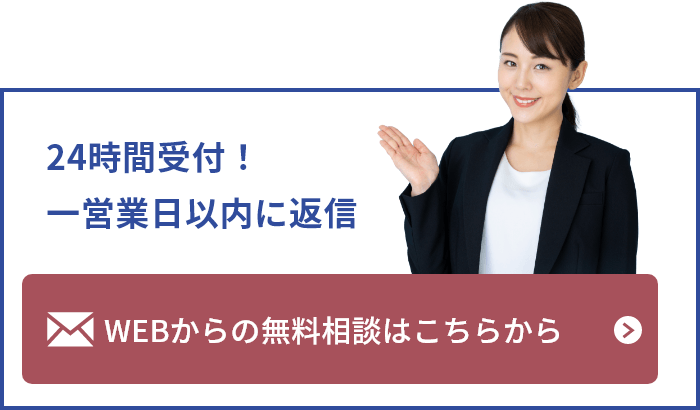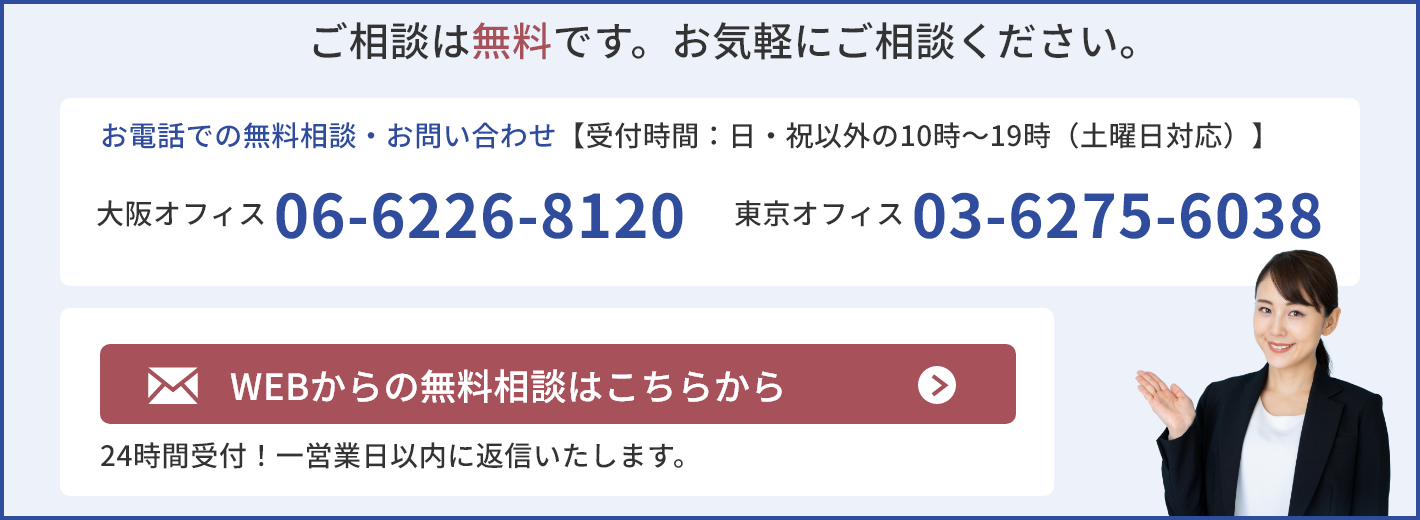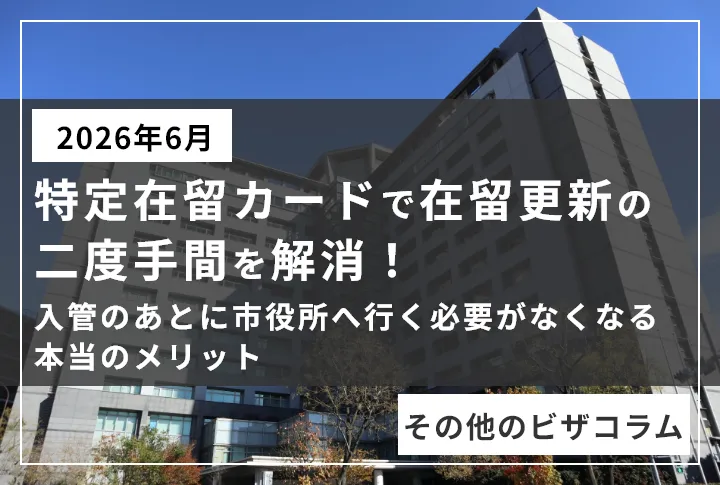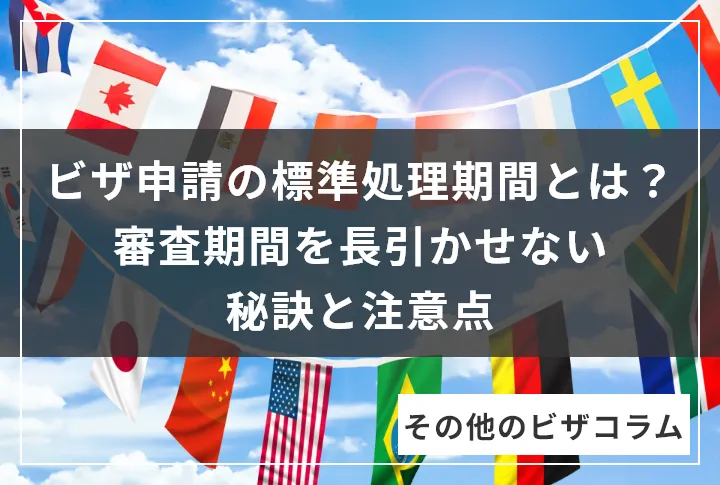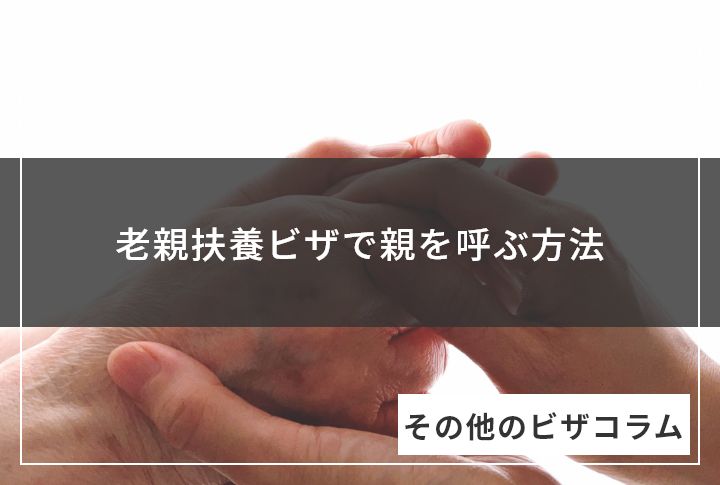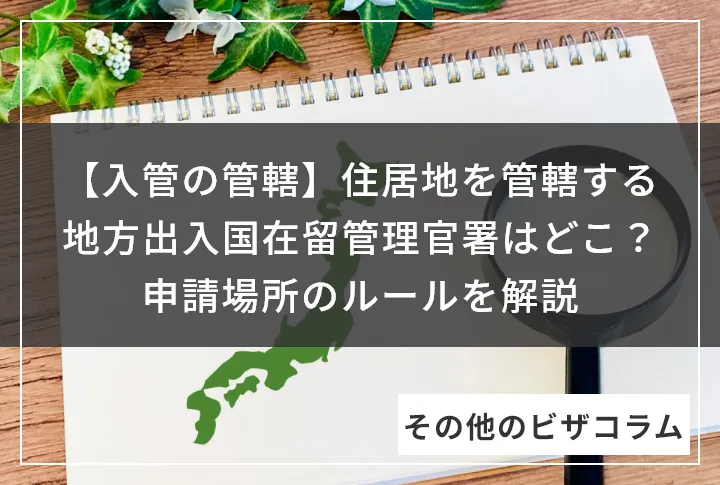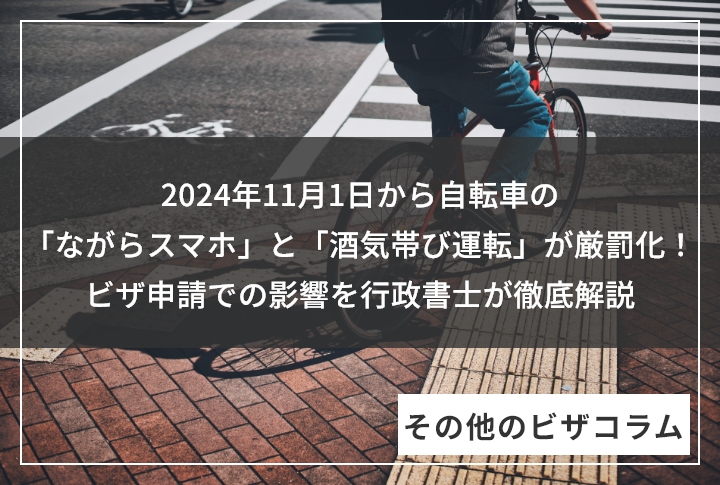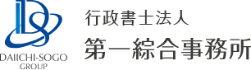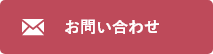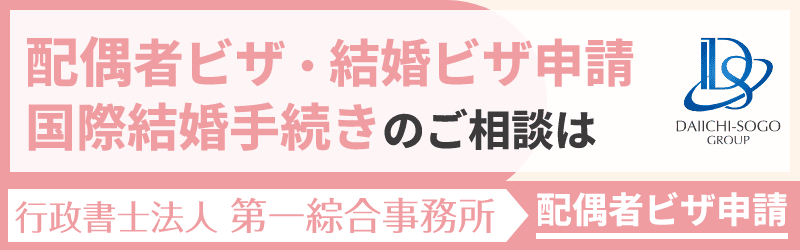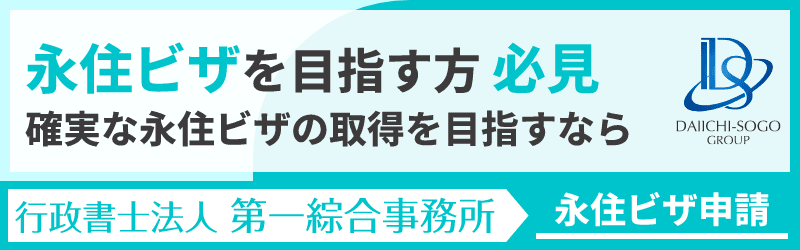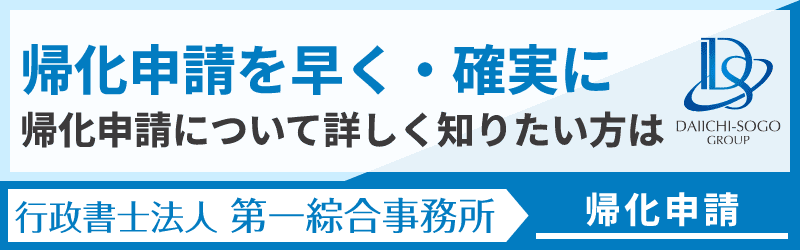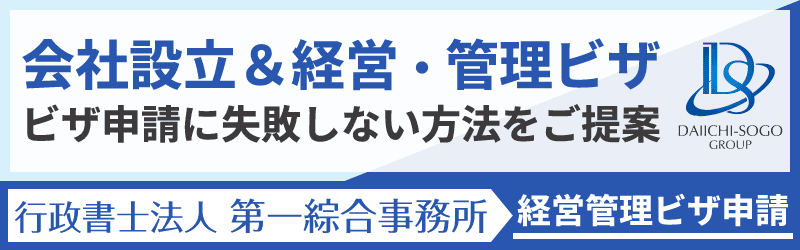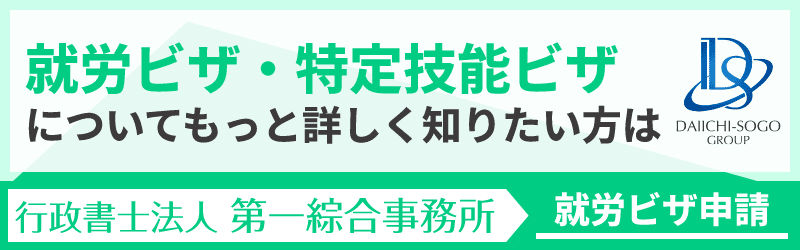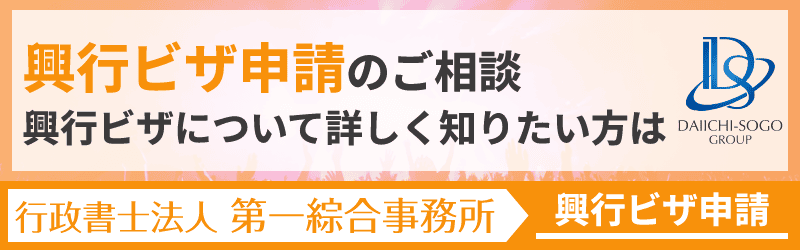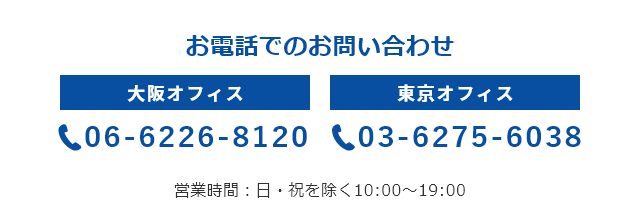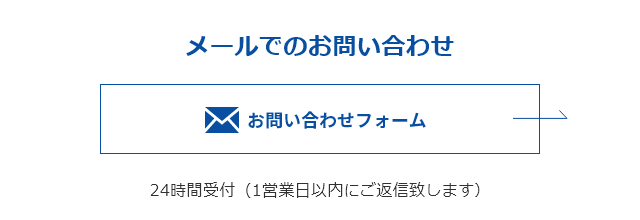外国人の運転免許切替が2025年10月~厳格化!観光客は対象外に!行政書士が「外免切替」制度のポイントを解説
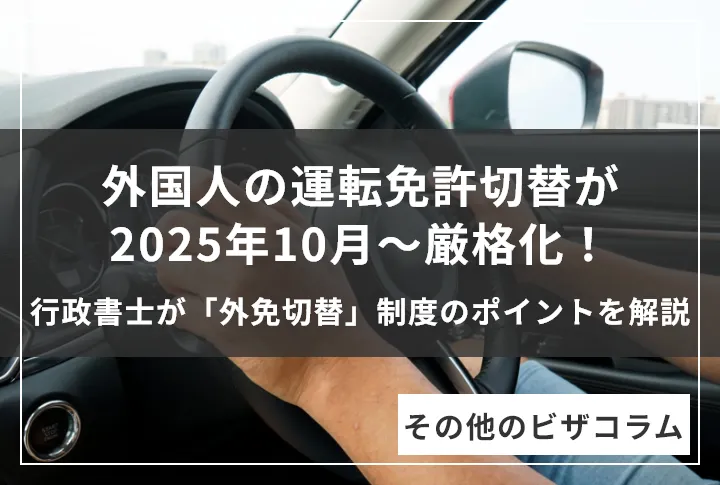
海外で運転免許を取得した外国人が,日本で運転するために日本の運転免許証に切り替える「外免切替制度」というものがありますが,この制度が2025年10月1日から厳格化されました。
背景には,外免切替を利用した一部外国人による交通事故や無資格運転の増加があります。今回の厳格化で,留学生や仕事で車を運転する外国人に少なからず影響を及ぼすことが予想されます。
本コラムでは,行政書士の視点から「今回の改正で何が変わったのか」「どのような点に注意すべきか」をわかりやすく解説します。
Index
1.外免切替とは?制度の基本と対象者
「外免切替(外国免許切替)」とは,外国で正式に取得した運転免許証を,日本国内でも有効に使用できるように切り替える制度のことです。
本国で適法に運転免許を取得した外国人が,改めて日本で免許を一から取り直す負担を軽減する目的で設けられたものです。
①管轄の運転免許センターで切り替え申請を予約
②筆記テストと技能テストを受ける
外免切替制度について,詳しく見ていきましょう。
1-1.対象者の範囲
外免切替は,日本に生活の拠点を持ち,日常的に運転を行う必要のある外国人の交通利便を確保することを目的として設けられた制度です。
外免切替の対象となるのは,「過去に外国で免許を取得し,その取得後に当該国に3か月以上滞在した実績を有する者」とされています。したがって,制度上の対象者は「どのような在留資格か」というよりも,外国で有効に取得した免許を保有し,その国に一定期間滞在していた実績がある者と定義されています。
これは,いわゆる“ペーパードライバー免許”や形式的な免許取得を防ぐための規定であり,実際にその国で運転経験を積んだことを前提としています。
一方で,「短期滞在」(観光ビザ)での入国者は本来対象外でした。
しかし実際には,ホテル滞在証明などで形式的に「住所確認」として切替申請が行われるケースも存在し,運用上の抜け穴となっていました。
1-2.国際運転免許証との制度の違い
国際免許証は条約加盟国間の相互承認に基づき,一時的な運転を認める制度であるのに対し,外免切替は日本に住所を有し,長期的に生活する外国人向けの恒久的な運転資格を付与する制度です。
そのため,国際免許証では日本国内で1年間の運転が可能ですが,外免切替で取得した免許証は日本人と同じく更新制となり,更新し続ければ実質無期限に有効となります。
| 比較項目 | 外面切替 | 国際運転免許 |
| 根拠法 | 道路交通法第97条 | ジュネーブ条約(1949) |
| 対象者 | 日本に住所を有するもの ※住民登録をしているもの |
条約加盟国間を一時的に訪問するもの |
| 有効期間 | 日本人と同様に更新制 | 発行日から1年間 |
| 目的 | 日本での恒久的運転資格付与 | 短期的運転許可(旅行・短期滞在) |
| 申請先 | 各都道府県公安委員会 | 免許発行国の公的機関 |
また,スイス・ドイツ・フランス・台湾など,一部の国では,自国免許証および日本語翻訳文で日本国内の運転が認められています。
ただし有効期間は「入国日から1年間」に限定されており,長期滞在・就労目的の者は外免切替が必要です。
参考:千葉県警察「外国運転免許証により日本国内で運転できる期間」
2.2025年10月の改正で変わったこと
今回の改正は,「警察庁による道路交通法施行規則の改正(2025年10月1日施行)」に基づいています。まずは,今回の改正でどのような点が変わったのか,全体像を整理しておきましょう。
| 区分 | 従来ルート | 改正後ルール |
| ①居住用件 | 形式的な住所確認 ※ホテル・友人宅などでも申請可 |
住民票の写し提出が必須 ⇒観光客は対象外 |
| ②在留要件 | 一時滞在でも申請可 | 短期滞在・観光ビザは不可 ⇒定住・就労・留学など中長期在留者が対象 |
| ③筆記試験 | 10問構成・7問正解で合格 | ・50問構成に変更 ・合格基準は正答率90%以上 ・イラスト問題廃止 ・交通法規理解を重視 |
| ④実技試験 | 発進・右左折・停車など簡易試験 | ・横断歩道,踏切。交差点対応など追加 ・安全確認・法規遵守を詳細評価 |
| ⑤手続き | 申請者の滞在形態により運用差あり | 全国的に基準を統一し,申請書類の厳格化・住民票確認の徹底 |
続いて,この中でも特に実務上影響の大きい3つのポイントを詳しく見ていきます。
参考:警視庁「令和7年10月1日施行・改正道路交通法施行規則について」
2-1.ポイント① 住民票の提出が義務化 ― 観光客は切替不可
2025年10月施行の改正道路交通法施行規則により,外免切替の申請手続において「住民票の写し」の提出が原則必須となりました。この改正は,形式的な「住所確認」を廃止し,申請者が日本国内に実際の居住実態を有しているかを確実に確認するための措置と言われています。
したがって,「住民登録がない=日本に住所を有しない者」は,申請そのものが受理されなくなりました。
・観光客(短期滞在者)
住民票がないため,外免切替の申請は原則不可となります。
今後は,ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証または自国免許,および日本語翻訳文を利用して運転する必要があります。
・企業(外国人雇用担当者)
ドライバー職の採用や業務運転を伴う職種では,採用時に住民票の有無・在留カード記載事項の確認が必ず必要となります。
特に,特定技能・など就労資格者の在留期間に応じた免許有効期間管理が求められます。
・日本に在留する外国人本人
外免切替を希望する場合は,まず住民登録を完了させることが必要です。
※住民票の取得には,入国後14日以内の転入届提出が必要(住民基本台帳法第30条の45)。
※住民登録の手続きを怠ると,免許申請だけでなく,健康保険・年金加入などにも支障が生じるため注意が必要です。
2-2.ポイント② 筆記試験が大幅に難化 ― 問題数50問・正答率90%以上
外免切替の筆記試験(学科試験)は,2025年10月以降,これまでの10問構成(イラスト+2択式)から,50問構成の文章問題形式へと大幅に改訂され,また,内容も「交通ルールの知識テスト」ではなく,「日本の交通法規理解の確認」という形式に変わっています。
そして,出題形式はすべて2択式のままですが,内容は従来の「標識の意味」「進行方向」などの基礎理解にとどまらず,道路交通法上の規定・優先順位・運転者責任など法的要素を含む問題が中心となっています。
警察庁が示す新基準では,出題分野は以下のように分類されています。
- 法規理解分野
道路標識・標示,徐行義務,優先道路,歩行者保護など - 安全運転行動分野
夜間運転,悪天候時の対応,追い越しや車間距離の保持 - 事故防止分野
飲酒運転・スマホ操作などの禁止事項,危険予測問題 - 道交法遵守分野
運転者の責務・免許携帯義務,交通違反時の罰則
特に,日本語での正確な理解力と法条文的な読解力が求められる点が,今回の改正の最大の特徴です。
従来の「感覚的に選べるイラスト問題」は廃止され,日本語の長文を読み取り,選択肢を正確に判断できるかが合否を分けるようになりました。
従来は「10問中7問正解(70%)」で合格できましたが,改正後は「50問中45問正解(90%)」が求められます。これは,5問のミスで不合格という極めて高い基準です。
試験時間も延長され,問題内容も交通法規・安全意識・運転マナーを包括的に問う形式に変わっています。
この変更により,日本語が十分に理解できない外国人や,母国語環境で免許を取得した人にとっては格段に難化します。
試験場によっては英語・中国語・ベトナム語などの翻訳対応も行われていますが,問題文は「日本法の概念を正確に翻訳」したものであり,日常会話レベルでは解読が難しいケースも少なくありません。
2-3.ポイント③ 技能試験の評価基準も“新規免許並み”に
また,筆記試験だけでなく,技能試験(実技)も全面的に見直されました。
従来の技能確認は「発進・右左折・停車」などの基本動作を中心とした簡易試験でしたが,改正後は日本人が普通免許を新規取得する際の試験項目と同等の評価基準に統一されています。
- 横断歩道接近時の徐行義務・歩行者優先の判断
- 踏切進入時の一時停止・左右確認
- 交差点での合図・進路変更手順の厳格化
- 安全確認のタイミング(ミラー・目視・方向指示器)
- 法定速度遵守・徐行判断・停止線での完全停止
これらの項目は,「運転行動の再現性」「安全確認のタイミング」「法規遵守意識」を総合的に評価するものです。単なる「技能確認」ではなく,交通倫理の理解度まで評価対象に含まれる点が特徴です。
そして,技能試験は,筆記と異なり採点官による総合評価の側面が強く,交通法規の遵守状況や,指示速度・安全確認・車両操作の滑らかさ,周囲の危険予測能力などが加点・減点対象になるとされています。
3.外国人ドライバーを雇用する企業が注意すべき実務対応
外免切替の厳格化により,外国人本人だけでなく,外国人を支援する企業の担当者等にも新たな実務対応が求められます。
これまでであれば,来日直後に外免切替を済ませ,すぐに業務運転へ移行できたケースも多く見られました。
しかし今後は,筆記・技能試験の難化により,切替までに一定の準備期間や再試験期間が発生する可能性があります。
特に企業の人事・総務担当者は,在留資格・住民票・外免切替の進捗管理も合わせて対応していく必要が求められます。
①免許証コピーの定期確認制度の導入
採用時だけでなく,毎年の契約更新時に外国人従業員の免許証コピーを回収・確認する。
期限切れや更新漏れを防止し,管理表で有効期限を一覧化する。
②免許切替完了までの“運転制限ルール”を明文化
外免切替が完了するまでは,社用車の運転を禁止し,同乗指導または社内講習に限定するなど,明文化された社内ルールを就業規則・雇用契約書に反映する。
③任意保険の「運転者限定条件」を確認
保険会社によっては,外国免許または外免切替直後の運転者を補償対象外とするケースがある。
「補償対象範囲(運転者年齢・資格制限)」を見直し,外国人従業員の追加登録を行う。
④労災・通勤災害時のリスク説明
免許未取得状態で社用車を運転した場合,労災認定・保険適用が受けられない可能性があることを社内研修で周知する。
4.なぜ今,厳格化が行われたのか ― 改正の背景と目的
今回の制度改正の背景には,外免切替を利用した免許取得者の急増と,それに伴う交通事故・違反の増加があります。以下にて,改正の背景の詳細をご説明します。
【背景① 外免切替利用者の急増と制度の形骸化】
近年,インバウンドの拡大や外国人従業員・留学生の増加により,外免切替の申請件数が急激に増加しました。
本来,外免切替は「日本に居住実態があり,継続的に生活する外国人」を対象とした制度ですが,一部では短期滞在中の観光客がホテル滞在証明などを用いて形式的に免許を取得するケースも見られるようになりました。
このような運用は,制度の本来趣旨である「生活基盤のある外国人への交通利便性確保」から逸脱しており,警察庁・都道府県公安委員会の間でも課題視されていました。
【背景② 外免切替保持者による事故・違反の増加】
さらに深刻なのは,外免切替保持者による重大事故の発生です。
特に近年は,外免切替で取得した免許を持つ外国人によるひき逃げ事件,高速道路逆走事故などの事故が相次ぎました。
事故後の調査では,筆記・技能試験が簡易的で,日本の交通法規理解が不十分なまま運転していた例も確認されています。
警察庁はこうした事案を受け,外免切替制度の運用実態を全国で点検し,「実際の居住確認」「交通法規理解」「運転技能評価」を厳格化する方向で見直しを進められています。
【背景③ 制度の原点回帰:「定住外国人中心」へ】
これらを踏まえ,2025年10月の改正は,外免切替を「観光客中心」から「居住外国人中心」へ原点回帰させる政策的転換と位置づけられています。
警察庁の運用通達でも,「外免切替は日本に住所を有する者を対象とする」と明記され,住民票提出義務化・試験難化など一連の改正はその流れの一環といえます。
外免切替は,本来「生活者としての外国人」の交通参加を支える制度です。今回の厳格化は,制度を本来の趣旨へと戻す「健全化」が目的であって,単なる制限の厳格化ではありません。
5.まとめ
本コラムでは外免切替の厳格化についてご説明しました。今回の法改正は,外国人本人の負担増という一面的な話ではありません。むしろ,日本社会全体が「外国人をどのように受け入れ,どのように共に生活していくのか」を改めて問い直すきっかけとも言えます。
企業の立場から見れば,単に「免許が取れるかどうか」ではなく,採用後の安全管理・労務管理・法令遵守の在り方を見直す契機となりました。採用時点での在留資格確認や,外免切替が完了するまでの業務設計,保険・労災対応の整理など,企業に求められる管理レベルはこれまで以上に高まっています。
外免切替に関連して,外国人従業員や外国人に従事してもらう業務内容について何かお困りごとがございましたら,外国人に関する手続きを専門とする行政書士法人第一綜合事務所までお気軽にお問い合わせください。